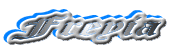
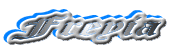
〜フレイア〜
| この話は、少々特別な設定になっています。 ウォルフガング・ミッターマイヤー元帥は早々と退役し、 今は新帝国の国務尚書として国家の中枢にいます。 彼とエヴァンゼリンの間には養子のフェリックス、被保護者のハインリッヒ・ランベルツ、 実子であるヨハネスとフレイアの双子、そして末子のマリ・テレーゼがいます。 ヨハネスとフレイアはオスカー・フォン・ロイエンタールが死んだ12月16日生まれです。 だからではないでしょうが、 ミッターマイヤーはヨハネスが自分たちのように軍人になってほしいと思い、 できればそのそばにはフェリックスがいてほしいと思っています。 エヴァには実子を産んでほしい、というのが作者であるわたしの願望です。 話はフレイアとヨハネスの双子が ロイエンタールの死んだ12月16日に生まれるところから始まります。 |
Freyia(フレイア) (1)
その日、双璧のふたりは、ロイエンタールの官舎でいつものように酔っぱらっていた。
「なあ、変な夢を見たぞ」とロイエンタール。その目はすわっている。
危険な状態だ、とミッターマイヤーは思った。
そう思うミッターマイヤーも、少々心許ない状態になっている。
「どんな夢だ?」
「おれはミッターマイヤー家の赤ん坊になっているらしい」
「は?」
「なぜか、おれそっくりな息子もいた。
そしておまえがおれそっくりの息子を抱いて、おれの前に見せてうれしそうにささやくんだ。
『ほら、これがお兄ちゃんだぞ』、って」
「・・・・・・・なんだ、それは?」
「つまり、おまえにはおれそっくりな息子が生まれて、おまけにおれも生まれるらしい」
ぶっ!とミッターマイヤーがワインをふきだす。
「もったいないな、410年ものの逸品だぞ」
「そ、それはわかっているが・・・・・あまり想像したくない家庭だな。
だいたい、何でおれとエヴァの間に、卿そっくりの赤ん坊が生まれねばならんのだ?」
「わからん。おれとおまえが結婚でもして、おまえがおれの子を産むのなら・・・」
「や、やめてくれ!想像でもしたくない!!」
「そういえば、母親の顔は出てこなかったな・・・」
「だからやめろって!」
「おまえはそんなにおれが嫌いか?ウォルフィ」
ミッターマイヤーはそう呼ばれて、一瞬、くすぐったそうな表情になる。
甘えたような響きのあるその呼び方。
彼をそう呼ぶのは、この世にただ一人しかいない。
愛する妻さえ呼ばない、その名前。
そして、目の前にいる帝国の双璧の片割れをファーストネームで呼ぶのも、おそらく自分一人。
・・・ミッターマイヤーは頭を振る。
「・・・・・・そ、そういう問題ではなかろう!?だいたいおれは男、卿も男だぞ!」
「そこが問題だな・・・いったいどっちが生むのだろうな」
「おれはおまえの子どもなんて産みたくない」
「ほう、ならオーベルシュタインの子だったらいいのか?」
「な、何でそこでオーベルシュタインが出てくるんだ!死んでもいやだ!!」
「安心しろ、嫌がらせだ」
「・・・おまえなぁ・・・」
「・・・しかし、だな、ミッターマイヤー。おまえのような女がいたら、おれの漁色もおさまるだろうさ」
「またそういうことを!!」
ミッターマイヤーは真っ赤になって叫ぶ。
しかし、すぐに真顔になる。
「でも・・・」
「?どうした?ミッターマイヤー?急に考え込んで」
「・・・」
「そうか、おれの子供を産みたいのか?」
「その考えから離れろって!」
「そうか、おれはおまえの子だったら産んでもいいぞ」
「冗談でもそう言うこと言うな!!」
「本当におまえをからかうとおもしろいな、ウォルフ・デア・シュトルム」
「・・・・・・あのなぁ、いい加減にしろよ、おまえ」
「おまえは本当にからかいがいがある。見ていて退屈しない」
「・・・」
「ん、どうした?」
「あのな、まじめに言うから、よく聞け。一回だけ言うからな」
「ああ」
「もしも・・・もしもおまえがおれの家に生まれたら、
今度は幸せな子ども時代、というものをじっくりあじあわせてやるぞ」
「・・・期待しておこう」
「しかし、それはあくまで夢でしかないな。
おれはこの出征が終わったら、子作りに励むんだ。
そんなおれのところにおまえが生まれ変わってくるのなら、おまえはもう死ななければならん。
それはなかろう?」
「・・・ああ、そう願いたいものだ」
オスカー・フォン・ロイエンタールは目を細める。
そして、目の前にいる友の髪をくしゃくしゃにかき回そうと、手を伸ばす。
そして・・・友のパンチが、見事なまでにきれいに顔にヒットしていた。
それから数年、己の半身を失ってから2年。
ミッターマイヤーはふと、そのときのことを思い出す。
幸せだったあの日。
そして、考えてもみなかった、いや、予感はあったが、考えたくなかった、ロイエンタールの謀叛と死。
残されたロイエンタールの息子フェリックス。
ロイエンタールの子なのだからそっくりなのも当たり前だ。
では、今生を受けようとしている自分の子は、彼の生まれ変わりだろうか?
しかも今日は、彼が天上へと旅立っていった日ではないか。
あのときは冗談だと思っていたことが、現実味を帯びてくる。
馬鹿なことばっかり考える!そう思い、頭を振る。
しかし、耳に聞こえてくる、あの懐かしい声、甘い、彼にだけ優しい響きを聞かせてくれる、テノールの声。
(ウォルフィ、愛している)
(もしおれが生まれ変わったら、おまえはおれがわかるか?)
(生まれ変わっても、おれを愛してくれるか?)
「・・・ああ、愛してやるぞ、オスカー」
・・・ただし、今度は親と子として、だ。
病院へと向かう地上車のなかで、ミッターマイヤーはそんなことを考えている。
帝国歴4年12月16日、午前2時。
銀河帝国を実質上支配しているふたりのうちの一人、新任の国務尚書ウォルフガング・ミッターマイヤーは
真夜中のフェザーン大学附属病院の産婦人科の廊下で、なすすべもなく廊下を行ったりきたりしていた。
こんな夜中に廊下にいるのは、ミッターマイヤーと護衛役のバイエルラインのみ。
気ぜわしげな乾いた靴音が響く。
産室から漏れ聞こえてくるモニターの胎児の心音が、その靴音と重なって聞こえる。
心音というものは、こんなに大きいものなのか。
まさか外まで聞こえるとは思わなかった、とミッターマイヤーはぼんやり考える。
すぐそばにエヴァがいるかのような錯覚すら覚える。
その心音は、心なしか力強く聞こえる。
生きたい、生きたい、そう赤ん坊が訴えているようだ。
病院に入って、もう3時間以上たつ。
その間に自分がしたことといえば、
こんな時にもそばにいるバイエルラインからサンドイッチをもらって食べたこと。
もちろん味などわからない。
そして、廊下を何度となく行ったり来たりしたことだけだ。
こう言うときは男というものは無力だ、とつくづく思う。
せめてそばに行ってエヴァの手を取ってあげたい、
そう思うが、思いのほか難産で医者に止められてしまった。
何しろ2ヶ月も早い出産だ。
母体にも負担がかかっているだろう。
赤ちゃんにも・・・。
「母体の状態によっては、赤ちゃんをあきらめてもらうかもしれません」
と医者は言った。
「最善は尽くします。しかし、ご覚悟をお願いします」とも。
実のところ、連絡を受けてからとるものも取り合えす飛び出してきた。
書類の山はどうなっているだろうか?
そんなことを、こういう場合にさえ気にしている自分がちょっとおかしくもある。
エヴァは必死で、死への恐怖と戦い、命を生み出そうとしているのに。
分娩室の外へも、エヴァの声が聞こえてくる。
産みの苦しみというのだろうか?
いや、それ以上のものとエヴァは戦っている。
ミッターマイヤーにはそう思えた。
エヴァの声が大きくなると一瞬赤ちゃんの心音が聞こえなくなるような気がして、
ミッターマイヤーはどきりとする。
昔、聞いたことがある。
赤ちゃんが生まれるとき、生まれてくる赤ちゃん本人は息が詰まるほど苦しいのだ、と。
窒息することもある。
それでも「生まれたい、生まれたい」という意志を持って、
自分から産道の中で体を回して出てくるのだと。
自分と、エヴァの子は、今、生まれたい、生まれたい、と叫んでいる。
エヴァの声が大きくなり、赤ちゃんの心音も大きくなる。
若い看護婦の「がんばって!」という声も聞こえる。
ミッターマイヤーは、自分の手のひらに汗がにじんでいるのを感じる。
思い切り握りしめていたのだ。
自分がまるでお産をするかのように。
ミッターマイヤーの中で、あの日の、たわいのない、冗談のように思えた会話がよみがえる。
おまえが生まれてくるのか?
それとも、生まれたくないのか、オスカー、そんなことはないだろう?
この世界は、おまえが知っているよりもずっと美しいんだぞ。
今度生まれてきたら、おれがそれを教えてやる。
おれと、エヴァで、幸せな家族、と言うものを味あわせてやる。
約束しただろう?
「生まれてきていいんだぞ、オスカー。そうしたら、今度はおまえを幸せにしてやる」
そうつぶやくミッターマイヤーだった。
やがて、一段とエヴァの悲鳴が大きくなる。そして・・・。
赤ちゃんの心音が聞こえたのは、わたしの実体験です。
娘を産んだとき、産室の前が病室でしたけれど、ほかの妊婦さんが出産するときに
やけに大きな心音が聞こえてきた記憶があります。